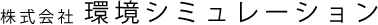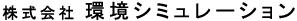風害評価の際に必要ないろいろな風について説明しましょう。
●勾配流
風工学では地上付近では天空面(境界層より上)に比べて風が乱れています。
平たく言えば、上空に比較して地表面の風速は遅いということです。これは、地表面に建物などの突起や地盤の起伏があって、風が随時はく離して渦が発生するからです。
この風が遅くなる程度を粗度区分と言い、風速の鉛直分布はべき乗則に従う勾配を持つ流れ-勾配流-になります。
粗度区分はⅠからⅤに分かれており、Ⅰが海辺や砂漠など障害物がほとんどない場所で、地表面近くまで上空風と変わらない分布になります。
Ⅴは日本で言えば東京の西新宿のような超高層ビルが林立している場所で、地表面の風速は上空に比べて著しく減衰します。ⅡからⅣはこれらの中間であり、通常の市街地は粗度区分でⅢかⅣが選ばれるのが普通です。
このような風の設定は、数値シミュレーションでは境界条件と初期条件で設定し、風洞実験では適当な乱流格子とラフネスブロックの組み合わせで設定します。
●吹き降ろし
一様な風が矩形のビルに当たると、風は衝突点を中心に等方的に拡散します。
衝突点から真下に向かう風は吹き降ろしとなり、風上側のアプローチ域に逆流を起こします。建物に風が当たる直前の地表面に近い領域では、周辺の風とは逆方向の風が吹くのです。ビル風の特徴として覚えておくべきでしょう。
またビルの直近では風の衝突点が地表面より上方なので風は下向きに吹く事も大きな特徴です。 勾配を持った流れでは風の衝突点が地表面から遠くなるため、逆流域の風も建物直近で上方から吹く風も、粗度区分に応じて小さくなります。
衝突点の真下から外れた領域は、横なぐりの風になる事は言うまでもありません。
●加速域の風
風に面した建物の角部では風が速くなります。
これは本来建物に当たるはずの風が建物のボリュームでさえぎられて風の行き場が脇の角部に集中するからです。
この風が早くなる領域を「加速域」と呼びますが、建物の壁面が風に正対している場合は加速域は建物の両側に均等に出来ますが、壁面が風向に対して傾斜している場合は片方に集中して出来る事があります。
計算領域の、風に垂直な断面積に対して建物幅が大きいほど、加速域は大きくなる傾向にあります。
これを避けるため、数値シミュレーションでも風洞実験でも、建物の見つけ断面積は、計算領域(風洞)の風が通る断面積に対して5%以下の割合である事が必要とされます。
●剥離渦
建物などの角部は以前も述べたように特異点(Singular Point)です。
流体力学でいう特異点というのは、流れに対する法線面が存在せず法線方向ベクトルを定義出来ないという事で、流れは直進運動を維持できず向きを変えます。
その結果として渦が特異点の直後に生じます。 これが流れの剥離(Detachment)です。
渦の内部は風(外部流)の方向と反対方向に回転しているので、通常は大きな負圧が直近の建物上面あるいは壁面に発生します。
建物の風への正対面のエッジより後方で負圧が生じるのは、この現象が原因です。剥離した渦の流線は更に後方で建物壁面ないしは地表面で合流します。
これを再付着(Attachment)と呼びます。再付着点より後方では渦が消失し、流れの方向は従来の風の方向に復帰します。
●後流渦
建物の後方では、加速域を通過した速い風や各部位で剥離した渦などの流れが輻そうして非常に複雑な流れになります。
しかし建物の真後ろでは、風が建物ボリュームでさえぎられる関係で風速は著しく減衰します。またその部位では大きな渦が発生しているため、流れは穏やかな逆流となります。
このような領域を「後流域(Wake)」、その流れ全体を「後流渦」と呼びますが、建物代表長さの5倍程度の距離で、風速鉛直分布が与えた外部風の分布に復帰するのが普通です。
●離隔距離の小さい場所の風
「離隔距離」と言うのは当該建物に隣接する建物との距離のことです。
吹き降ろしの風あるいは加速域の風は、建物間の地表面に近い狭い範囲に集中すると更に風速の大きな風になります。
これを回避するには離隔距離を稼ぐ、即ち隣接する建物との距離を空ける事が非常に有効です。