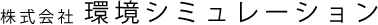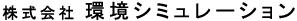日本のことわざに、「風が吹けば桶屋が儲かる」というものがあります。これは、因果の関係をつづったもので、「大風が吹くと砂ぼこりが舞う」、「舞い上がった砂埃が目に入って失明する人が増える」、「失明した人は三味線弾きになる」、「三味線の売れ行きが伸びる」、「三味線の皮に使われる猫が減る」、「猫が減るのでネズミが増える」、「ネズミが増えるので桶をかじられる」、「桶を買う人が増えるので桶屋が儲かる」というものです。様々な現象に、「原因と結果」の関係を見つけ出し、その連鎖を考えることで、「風が吹けば桶屋が儲かる」という論理を導き出したのでしょう。このことわざは、株屋さんが好んで使うエピソードだそうです。株式の売買市場では、「何でもないと思われる些細な出来事が、ほとんど関係がないと思われていたことに影響し、思いもよらぬ結果となることがある」と真顔で信じ、また信じさせ、社会の様々な出来事をネタにして、株の売買を行う人の逸話があふれているようです。そうした人々は、どのように「風が吹けば桶屋が儲かる」というような結構怪しい、何らかの因果の関係を見つけ出し、それを人々に「確かかもしれない」と信じ込ませることができるのでしょうか。天気予報で大風が吹く予測が出れば、桶製造会社の株を安く購入し、大風が吹いた後に、人々にその因果を信じ込ませて一時的に株値を高騰させ、反動で下落する前に売り抜けて、儲けるのか、知りたくなります。「詐欺みたい」とも思いますが、最初に因果を見つけて喧伝する人が、その因果を信じており、欺く気など全くない純な人物であれば、もちろん詐欺にはなりません。その怪しい因果を信じた人々の自己責任ということになるのでしょうか。
ただ、ここで教科書的な株式売買の常識を開陳すれば、株式の値上がり(キャピタルゲイン)は基本的に企業の成長すなわち価値創造の増加もしくはその期待によって、生じるものとされているようです。成長する企業を、客観的なデータ分析と企業経営者の特性を心眼で見抜き、年単位あるいは数年、数十年単位で長期に企業の成長を見守り、その株式を保持して成長の果実としての株式の価値増大を期待することが、投資家の正しい在り方といわれています。成長しない企業、定常状態にあるような企業、もしくは衰退する産業を担う企業の株式の価値増大を期待しても、長期保有する意義はないといえるでしょう。
株売買の世界には、いわゆるデイトレーダーと称される人々がいます。多くの方々にはなじみがあり、ここで改めて解説する必要はないようにも思いますが、デイトレーダーとは、株式やその他の金融商品を一日のうちに買い付けや売却をして、その日のうちに取引を完了させる投資家を指します。デイトレーダーは、長期的な企業の成長や縮退も考慮するかもしれませんが、そのことよりはむしろ、様々な要因で変動する短期的な価格変動を利用して利益を得ることを目的としています。デイトレーダーは、様々な要因で変動する価格変動を数学的な分析や、市場動向の分析から、迅速な売買を実行します。短期的な価格変動は、企業成長の結果得られるものではありませんので、基本的にはゼロサムゲームといえるかと思います。
ゼロサムゲームでは、利益を得られる参加者の利益は、他の参加者の損失と等しい状態を指します。全体の利益と損失の合計はゼロになります。デイトレーダーが活躍する短期的な売買を繰り返す株式市場は、ゼロサムゲームの典型と思われます。ただこの株の売買市場では、売買を斡旋する証券会社のみが手数料収入で恒常的に利益を得ます。ゼロサムゲームの典型は賭博です。「てら銭」をとる胴元のみが恒常的に利益を得ます。筆者も長く、日本のジャンボと称する「宝くじ」を定期的に購入していますが、この宝くじも、賭博です。典型的なゼロサムゲームです。日本の「宝くじ」では、胴元の「地方自治体」は、非合法の賭博業者よりも、更に高率な「てら銭」を得ていると言います。ちなみに多くの人がそうであるように、筆者もこの「宝くじ」賭博は数十年続けていますが、トータルで全く利益を出していません。そうとは理解はしていますが、これからも、胴元に多くの「てら銭」を収め続けることでしょう。
デイトレーダーの多くは、このゼロサムゲームで、大きな利益あるいは大きな損失を得る可能性を増大させるシステムとして、証券会社から資金や株式を借りて行う信用取引を利用しているようです。実物の売買であれば、手持ちの資金や手持ちの株で売買するわけですので、損失があったとしても手持ち資金の損失だけで済みますが、多くのデイトレーダーは、信用取引により自己資金以上の取引を行います。レバレッジ(梃子の原理ですね)を効かせて売買を行い、利益の期待値を増出させます。ただし利益も大きいですが、損失もレバレッジが効きますので自己資金以上となります。最近、米国で活躍する超有名な日本人野球選手の専属通訳が米国のスポーツ賭博にはまり、その野球選手の預金を横領した事件がありました。胴元は、掛け金の総額に比例して「てら銭」を稼げますので、損失を出している賭博参加者にも鷹揚に掛け金を貸し付けます。事件を起こした専属通訳は、負けが込めば込むほど、この胴元から金を借りて賭博し、「てら銭」で胴元を太らせるだけのゼロサムゲームのメカニズムから逃れることができず、自滅してしまったようです。
デイトレーダーと信用取引を行う証券会社も、基本的にはこのスポーツ賭博を行う胴元と同じ仕組みを利用しています。デイトレーダーと信用取引を行って、リスクなしに稼いでいます。資金を貸し付ける「信用買い」では、デイトレーダーは証券会社から自己資金を大きく上回る資金を借りて株式を購入します。購入した株式は証券会社が担保として預かります。株価が上昇すれば、売却して利益を得ます。株価が意に反して下降してしまっても信用買いの期限が来れば、借りた資金を返済するため損失を承知して売却、返済し、借りた資金の利息も支払います。証券会社は利息と売買手数料で稼ぎます。株式を貸し付ける「信用売り(空売り)」は、デイトレーダーは証券会社から株式を借りて売却し、その売却費を担保として証券会社に預けます。預けた資金に証券会社は利息を支払いますが、後に株価が下がったときに預けた資金で株式を買い戻し、返却します。株価が下落すれば、売買の差額を利益として得られますが、株価が上がれば、その分損失が出てしまいます。一方、証券会社はデイトレーダーに手持ちの株式を貸す間に、現金を手にしてこれを運用し、運用益を得ます。借株の期間終了後にはノーリスクで有無を言わせず株式を回収し、株式の売買手数料でも稼ぎます。デイトレーダーは信用取引で自己資金にレバレッジを掛けて、大きく利益を得ることも可能ですが、大きな損失のリスクも負います。しかし証券会社はリスクなしに稼ぎます。賭博の胴元と変わりありません。
なお、筆者は「信用取引」を好ましくないと主張しているわけではありませんので、念のため。「信用取引」は「先物取引」と同じく市場取引の規模を大きくして、市場を安定的に運用するための重要な取引形態であると、中学時代に社会の教科書で習いました。筆者も当時、素直な少年でしたのでこれを無条件で信じました。今も教科書に書かれるほどの真実なんだと信じています。日本は、世界に先駆けて、江戸時代(1730年代だそうです)、大坂、堂島でコメの先物取引が行われた市場経済の伝統を持つ国とも習いました。世界的に自慢できることのようですヨ。最近よく話題に上るFX(Foreign Exchange)という名で知られている外国為替取引では、実需の数十倍もの為替取引が行われていると聞きました。株式の信用取引と違い、自己資金の数十倍のレバレッジを効かせた取引も可能だということでデイトレーダーの大きな活躍場所になっているようです。
デイトレーダーを長く続けるには、相応の利益を確保できていないといけないでしょう。ゼロサムゲームですからデイトレーダーが太るためには餌食が必要です。この餌食なる人は、いったい、誰なんでしょう。相応の資金を持ってデイトレーダーの世界に飛び込んだ素人然としたトレーダーもあるでしょう。また、短期の変動には無関心で長期の成長を当てにして、少々値下がりしても梃でも動かず塩漬けにし、少々値上がりしても売却など考えもしない、羊のようにおとなしい庶民投資家かもしれません。でもきっと、「風が吹けば桶屋が儲かる」という因果則を簡単に信じて、これを根拠にするような素人然としたトレーダーのような気がします。
短期(高周波)の変動を予測するのは、なかなかに難しいことです。長期の変動は、一応、ファンダメンタルズの変動(成長)に連動する因果が認められているようです。長期の変動に関して、「風が吹けば桶屋が儲かる」的な、少し怪しい因果律を耳にすることはあまりないのではないかと思います。しかし、長期の変動に関しても、世界情勢、特に政治の安定や経済の安定が大きな要素になりますので、口で言うほど簡単ではなさそうです。長期の変動にあっても、その因果を求めて、原因を特定し、将来を予測することはそれなりに難しいことです。いつものことですが、新年の始まりの時期に、新聞などでは、今年1年の経済予測や政治情勢分析が語られます。しかしこの予測、現代の天気予報程度に信頼できると信じている人がどの程度、いらっしゃるか疑問です。天気予報を引き合いに出しましたが、これはかなり信頼がおけそうな気がします。天気は、自然現象ゆえの不確実性を持ちますが、物理現象であり、因果則は明らかになっています。ただ、因果の因となる観測データが未だ不十分であることと、「バタフライイフェクト」などと称される非線形の因果則ゆえの複雑性のため、確度の高い(確率の高い)予測は、限られた時間範囲、地域範囲に限定され、範囲が増えるほどその確度は減少してしまいます。
短期(高周波)の変動は、確率的に生じる擾乱要素に影響されるため、その分析は難しいところがあります。最近は、AI(人工知能)、特にディープラーニングと称される統計解析(データからある種の規則性を見出す手法といって良いかと思います)によって、「風が吹けば桶屋が儲かる」的な因果則を見つけて、これを適用することがよく行われているようです。結果はデータ解析に供されたデータの性質によりますので、データの性質が異なれば、発見される因果則も違ってくることは、十分に予想されます。街のデイトレーダーばかりでなく、銀行や証券会社などに所属する専門職のトレーダーの方々も、データの分析により発見された、この「風が吹けば桶屋が儲かる」的因果則を上手に利用して、日々、運用に励んでいることと思います。
筆者も含め、流体解析の技術者は、現象の支配方程式という確固たる因果則に基づき、原因となるデザインから、実現されるであろうと考えられる予測を行います。ただ、短期(高周波)の変動は、同じく短期(高周波)の変動を持つ因果の因が原因するため、この因を十分に反映する解析を行わない限り、予測される因果の果の信頼性は大きくないことに注意する必要があります。信用できる予測は、全体的な大きなトレンドにあって、微細な変動に関してはその予測に怪しさが残ることは、株価予測と同じと考えています。