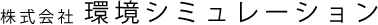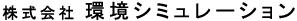前回のコラムでは主にビル風用の風洞模型実験とCFDについて述べました。
建築分野で使用する風洞は実験目的に応じていくつか種類があります。
前回のビル風のように風のみを問題とする場合の風洞を一般的風洞とすればそれ以外に温度成層風洞、風雪実験風洞、火災実験風洞等があります。いづれもその名の通り、風とあわせて気温や雪、火災を再現するためのものです。建築分野ではこれらの中で「温度成層風洞」が最もポピュラーと言えます。温度成層型風洞はヒートアイランド問題や大気拡散問題に対応するための風洞で、建築の分野に限れば東大生産技術研究所(東京駒場)の環境境界層風洞や東京工芸大学の都市温熱環境システムが有名です。特に東京工芸大は現在我が国の風洞実験研究拠点のメッカのひとつとなっており多数の風洞を有し数多くの成果もあげています。
筆者が大学院に入り初めて行った研究はこの温度成層型風洞を用いた実験的研究でした。
当時六本木にあった東大生産研には回流型の大型風洞がありましたが、筆者の実験は別棟にあった小型の吹き出し型温度成層風洞を用いて行いました。当時東大でDRを取得・卒業され上述の東京工芸大学に着任されたばかりのO教授(現同大学名誉教授)に手取り足取りのご指導をいただきました。
筆者が行った研究内容はヒートアイランド現象の原点ともいえる現象、つまり地表面発熱(太陽受熱面等)や吸熱(池面等)の都市空間への影響を考察するというものでした。
風洞内で流入風に温度成層(分布)をつくり、さらに地面(風洞床面)には電熱シートを用いた高温パネルと冷水を用いた冷水パネルで地表面温度を模擬作成し実験を行いました。
前回のコラムでも述べましたが、模型実験の場合、一般に相似則が必要になります。相似則は実験と実物の現象の一致を保証するための理論で例えば流れで言うとレイノルズ数の一致が有名です。ビル風等の風洞実験の場合、相似則は不要ですが(理由の説明は略します)、温度成層実験となると事情は一変します。
実際の都市空間は大気境界層という大気の層内にあり、地表面温度の日変化や地形・気象条件により様々な温度成層状態が形成されます。この成層状態は浮力の影響程度によって流れが「安定~中立~不安定」と分類されます。例えば流入する風温度が地表面温度より高いと流れが安定側に働きます。大気拡散の状況はこの大気安定度に大きな影響を受けます。この安定度はあるパラメータ(慣性力と浮力の比率を示すもので、バルク・リチャードソン数と言います)によって定義されます。模型実験ではこのパラメータを一致させるために温度や気流を細かく調整することになります。詳細は略しますが大気境界層の問題は建築分野だけでなく気象学を含む学際領域的な大テーマであり乱流理論や境界層理論と合わせ従来より数多くの研究が行われています。
話を当時の実験に戻します。
この風洞は上記O教授の手作り的なところがあり、風洞自体の断熱性の維持や定常になるまでの時間調整、2次元性の確保等、実験を行う前段階の条件設定自体に多大な労力が必要でした。また測定においても大変神経を使いました。現在ではレーザーが計測に用いられることが多いですが、当時の計測では熱線風速計を用いました。非常に繊細なもので実験中何回も熱線を切断させてしまい、当時の指導教官のM教授から強いお叱りを受けたことを懐かしく?思い出します。筆者の当時の実験に比べれば近年は風洞性能や測定技術は大幅に進展しています。しかしそれでも風洞実験に熱を取り入れることは(熱を入れない場合に比べ)手間暇や神経を数倍使うことになります。結論的には温度成層風洞実験は基礎実験やCFDのベンチマーク用には有効ですが、実務(ケーススタディ)実験にはいわゆる「投資対効果」が薄いと言わざるを得ません。
近年では幸いCFDが力をつけてきており上述の実験で多大な労力を要する発熱量の設定、断熱性の確保や2次元性確保等の問題は容易にクリアーできます。
ヒートアイランド問題や大気拡散の問題は今後のサステナブル建築や都市を構築するうえで大変重要となります。CFDへの期待は一層高まりますが、CFDにも問題点はあります。
次回はこの温度成層実験の延長上にあるとも言える「CFDを用いたヒートアイランド解析」について述べたいと思います。