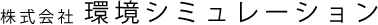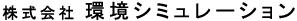対流により熱は局所から全体に良く伝わります。流体は、対流により効率的に熱を伝えます。小学校の理科の時間に、熱の伝わり方として、伝導と対流と放射の3つがあることを学びます。覚えておられるでしょうか。対流は、アルコールランプで熱したビーカーに入れた水がビーカー内で均一に温まる様子を例として説明されることが多いようです。地元の公立中学に進学するよりは、私立の有名中学を受験する小学生は、受験準備の一環として、この熱の伝わり方の3形態を理解するよう努めさせられます。
熱の伝わり方は、生活科学の一般として極めて大事なことなので、小学生のころからその原理を繰り返して学ぶことになりますし、中学受験で押さえておくべき知識としては、基本の一つになると思われます。熱の伝わり方は毎日の調理でよく使います。ゆで卵を作る、麺をゆでる、ジャガイモを煮るなどの調理は、材料内の熱伝導が支配しますので、典型的な熱の伝わり方の知識が必要になります。そのほか、電子レンジを使い、やかんや電気ポットでお湯を沸かし、冷蔵庫で食品を保存し、衣服で体を保温し、室内の温度を暖房器具や空調機で調整すること、すべて熱の伝わり方の知識が試されます。熱の伝わり方を学ぶことは、人の生活の知識の中で、極めて重要です。ただ、この熱の伝わり方3つの中で、対流によるの熱の伝わり方に関する小学校や中学校での学びに関しては、流体を扱う技術者として、違和感を多少抱きます。
小学校や中学校で学ぶ対流は、やかんによる湯沸かしなど、主に自然対流と呼ばれる密度差に働く重力(体積力)により流れが駆動されるものになります。温度が異なると、物質はその熱膨張率に従って膨張もしくは収縮して、密度が変わります。密度が変われば、重力加速度は同じですが、密度に応じて働く重力による力、すなわち重量が変わり、密度が低い流体の塊の下側に働く上からの重量による圧力は、同じ高さの周辺の圧力より低下します。このため、密度の低い流体の塊は上部に移動します。この流体の塊が持つ熱量が流れとなって移動するため、熱が伝わります。しかし、熱の移動の本質は、密度差による自然対流に限りません。流れ(液体でなくとも固体でも良い)があれば、流れの起源は別として、流れの塊そのものの移動により熱が移動し、結果として熱が伝わります。言い換えれば、一定の熱量を持った流体の移動に同期した熱の移動、熱の輸送が、対流という熱の伝え方の本質ではないかと思います。流れが、自然対流によって生じるか、あるいは、ファンやポンプなどの機械力によって生じるかは、問題ではなく、流体の塊が移動することによって、熱が移動することが、対流による熱の伝わり方の本質です。
生活の中で身近な熱移動に関し、家庭で、給湯器で沸かしたお湯が、蛇口まで移動することも対流による熱移動であり、空調機の吹き出し口から、冷却もしくは加熱された空気が、吹き出し気流となって移動することも、対流によるよる熱移動と教えるべきと思います。熱の伝わり方の3形態として、子供に、伝導と対流と放射という3つの形態があることを、知識として教える際、この対流に関しては、伝導や放射などが普遍的な物理現象として定義しているのなら、対流という熱の伝わり方は、流体などの物体の移動による熱の輸送と定義するのが自然であって、流れの起源として他の流れの起源もあるにもかかわらず、密度差による自然対流による熱の輸送を、伝導と放射と同列に扱うことは、概念の一貫性に反しています。初めて熱の移動を学ぶ小学生を馬鹿にする扱いだと思います。概念の一貫性に注意を払うのであれば、熱の伝わり方の3つの要素に対しては、伝導や放射と同列の概念であれば、熱量を持った物体が運ばれること、移動することで伝わる熱と定義すべきと思います。熱量を持ち、静止した固体は、慣性の法則により、力が働かない限り、自然には移動しないので、人が力を発揮して、人為的に運ばない限り熱は伝わりませんが、運んであげれば熱は移動し、結果、熱が伝わります。熱量を持った流体も、重力が働きかつ熱膨張率により温度が周囲と異なると密度差が生じることにより、自然に移動して熱が伝わりますが、重力が働かなければ、流体は密度差があっても移動しません。事実、重力がほとんど働かない、宇宙空間では、遠心力などにより人為的に体積力が生じる加速度を生じさせない限り、自然対流は生じません。伝導や放射は、宇宙空間でも不変原理として熱が伝わりますが、自然対流による熱の伝わり方は、宇宙空間では生じないのであれば、自然対流による熱移動を伝導や対流と同じように熱の伝わり方の3要素として説明することには、概念の首尾一貫性がありません。自然対流による熱の伝わり方は、特殊な例であって、伝導や放射と同列に扱うのであれば、熱量を持った物体の移動に伴う熱の伝わり方を対流として定義すべきです。皆さんは筆者の主張に賛成してくださいますでしょうか? (笑い)
熱の伝わり方で、特に固体から液体もしくは気体への熱の伝わり方は、工学的興味の深い現象です。伝熱工学という立派な学問分野もあります。特に相変化を伴う熱伝達である凝縮熱伝達や沸騰熱伝達などは、たとえCFD(流体シミュレーション)でも、マクロなモデリングを一切行なわず、原理方程式だけを解く手法を用いて再現することは、なかなかに難しい課題です。分子レベルの化学変化を追跡する必要のある燃焼のCFDや、液体の他、細かい気相や固相の物体を含む混相流のCFDなどとともに、チャレンジャブルな課題になっています。沸騰伝熱や凝縮伝熱など相変化を伴う伝熱は、脇に置いておいて、固体壁から気相または液相の流体への熱伝達を簡単に考えてみます。
まず、熱の伝わり方の3つの形態で、伝導、対流、放射での熱伝達形態で考慮すべきは、伝導と対流になります。放射も熱伝達に寄与しますが、固体壁から空気など気相への熱伝達を考える際は、いずれも無視されることが多いようです。これは、気相状態の流体が放射に関して透明度が高く、1m以内程度での熱伝達を考える際は無視されます。また固体壁から液水など液相への熱伝達を考える際は、液相の流体は放射に関して不透明で、液相内では放射伝熱は熱伝導と区別されず、熱伝導にまとめて扱われるが一般的のようです。
ということで、固体から流体への伝熱は、熱伝導と対流のみが扱われるようですが、ここで、大事なことが一つあります。固体壁は、法線方向に流体を通過させず、接線方向にしか流体は流れないことです。当たり前ですね。固体から流体への熱伝達は、固体表面から法線方向への熱移動を扱うのに、肝心の固体表面で法線方向の流体の速度はゼロで、流体の法線方向の移動による熱移動が固体壁近傍では期待できないのです。この付近では、固体壁面から流体への熱移動は、流体の熱伝導によってのみ行われます。流体が乱流状態にあると、あらゆる方向に乱れた様々な大きさの渦が生じており、この乱れた渦により、熱は効率よく、流れの接線方向にも、法線方向にも輸送されます。乱れによる拡散係数は、熱伝導に関わる流体の分子拡散係数よりはるかに大きく、固体壁面から法線方向への熱移動は、流体が乱流状態にあれば、効率よく行われます。しかし、固体壁の直近では、固体壁面に対して法線方向の流体速度が制限され、固体表面ではゼロですので、乱流の乱れによる熱輸送が期待できません。固体壁から流体への熱伝達を確保するには、この固体壁の直近に生じる壁面の接線方向におとなしく流れる(層流状態の)流れ(流体力学では粘性底層と言うそうです)を可能な限り薄くすることが重要になります。どのように薄くするかには多くの工夫があるようです。
ところで、最近はほとんど万人が見かけるようになったエアコンの室外機では、冷媒と空気の間での熱交換を行うため、フィン付きの熱交換器が見られます。フィンの間隔は結構狭く、数mmも無いように見えますし、フィンの幅も結構短く5cm程度もないように見えるかと思います。フィンの間隔が狭いので、フィンの間を通り抜ける空気は乱れて乱流の不規則な渦運動を形成することができず、乱れの無い層流状態で通過するように思われます。フィンとその間を通過する空気の流れの熱伝達を考えてみます。フィンをよく観察すると、フィン間隔が狭く特に乱れを惹起するような工夫もなく、空気の熱伝導(分子拡散)のみで熱伝達が行われていることが分かります。この熱交換機の熱伝達効率が気になるところですが、これは、結構よい効率になります。肝はフィンの間隔とフィンの幅になります。ご存知かもしれませんが空気の熱伝導率は約0.026W/Km、分子拡散係数(動粘性係数)は、0.000015m2/s程度です。フィン間隔を例えば1.5mm(0.0015m)として、その半分の距離を分子拡散により熱が伝導(分子拡散)で伝わる時間をオーダー評価すると(0.0015/2m)2/(0.000015m2/s)=0.04s程度となり、0.1秒もかかりません。フィン間を通過する空気の流速を例えば1m/s程度とすると0.04m程度のフィン間を通過する時間内に十分な熱伝達を行う時間が確保されることになります。この場合、フィン間隔を長くして空気とフィンの接触時間を長くしても、長くした部分ではフィンとの熱交換を終え、フィンの表面温度近くになって温度差がほとんどなくなった空気が通過するだけで、熱交換の効率を上げることには繋がりません。空気の熱伝導による熱伝達効率を上げるには、熱伝導が生じる方向(固体壁の法線方向)の間隔を狭くすること、空気を断熱材と思うのであれば、断熱材の厚みを薄くすることがカギになります。ただむやみに狭くすると、空気の粘性による流れの抵抗も大きくなり、空気がフィン間を十分な量、流れてくれなくなってしまいます。
エアコンの話から室内の熱伝達に話を変えます。室内の壁面から室内空気に熱が伝わる現象を考えると、壁面近くには空気の厚い断熱材を介して熱が伝わるための十分な接触時間が必要になることが分かります。しかしながら、接触時間は限られます。室内を3×3×3?程度として室内全体に分子拡散(熱伝導)で熱が伝わるには、(3/2m)2/(0.000015m2/s)=150000s、約41時間かかることになります。自然対流などが惹起され、乱れによる拡散係数が分子拡散の100倍程度になれば、1500s、約15分程度で室内の空気に壁からの熱が伝わると評価できそうです。
流体の関わる現象の分析では、こうしたオーダー評価による分析がしばしば役立ちます。CFDは、ほとんど、ブラックボックスによる解析でしたが、CFDの出した答をこうしたオーダー評価でつじつまが合っているか否か確認することは、ブラックボックス故の大きな間違いを避ける手法の一つとして重要と思っています。